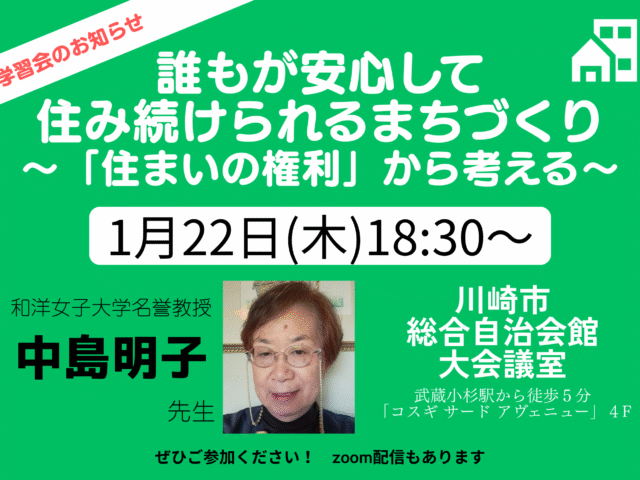一般社団法人 川崎建設業協会と懇談しました。
 7月1日(火)日本共産党川崎市会議員団は、一般社団法人川崎建設業協会の方々と懇談しました。同会から13名が参加され、以下のことを要望されました。
7月1日(火)日本共産党川崎市会議員団は、一般社団法人川崎建設業協会の方々と懇談しました。同会から13名が参加され、以下のことを要望されました。
1.PPP・PFI事業の発注について【継続】
川崎市は数年前より、PPP・PFI事業での発注案件が増えてきている。大きな利益が見込める大型施設の建設と運営や遊休地の有効活用など、民間企業の資金とノウハウを最大限に利用できるような案件には適していると思われるが、従来、市内業者へ発注していただいてきた案件については、大きなメリットがあるとは思えない。
BT方式(買取り方式)のような手法での発注は、市内業者にとって会社経営に大きな負担が掛かる。また、市外業者が事業(入札)に参加する事により、市内業者の受注機会が減少する。これらの理由からPPP・PFI事業の発注に際しては、慎重な検討をお願いしたい。
2.議会承認を必要とする建築工事費の見直しについて【新規】
現在、市から発注されている建築工事において、予定価格が6億円以上については、市議会での承認が必要とされる。議会承認案件の場合、落札から工事着手までに数か月を要す。人手不足が加速する中、受注者にとって大きな負担となり、発注者側の事務負担も大きくなっている。消費税率が上がり、建設資材及び労務単価が大きく上昇していることもあり、議会承認を必要とする金額の見直しをお願いしたい。
3.働き方改革及び人手不足への対応について【継続】
建設業においても働き方改革が本格的に導入され、週休2日制の導入や時間外労働の上限規制が始まっている。しかし、人手不足が加速し、会社経営に不安を抱えている中小建設業において、実現は厳しい。今後、工事を発注される際には、余裕を持った工期設定と適正な予算確保をお願いしたい。
4.麻生区内学校施設包括管理業務の同区以外への拡充に関する要望【新規】
近年、官公庁の施設は、新築ではなく長寿命化が主流となっている。
川崎市では、麻生区小中学校に包括管理を採用して施設管理と修繕工事の外注を開始した。2027年には全区にまで包括管理を拡大するとのこと。市内業者を活用する旨の方針も出されているが、実際には、市内管理者が全区の管理をすることは不可能であると思われる。
デメリットとして、
(1)発注者は自身の施設の状況、情報が把握できなくなる。
(2)契約範囲ごとに管理業者が変わる(可能性がある)ため、管理の方法が異なる。
(3)契約期限ごとに同じ業者が契約せざるを得ない状況になると、市が施設を管理できない。
(4)市外大手企業による管理が想定できるため、税収が他都市に流出する。
(5)一般的に、大手企業(想定)の経費は、中小企業に比べて高額で、最初は安価でも、前述のデメリット(1)及び(3)の状況下では、様々な理由を付して契約金額が上昇すると考えられる。
(6)それぞれの管理会社の基準で修繕を実施するため、施設の管理状況が異なる。市が情報を集めて総合的に計画を作る際などには大きな障害となる。市が有する施設の維持管理については、修繕工事を包括管理システムから切り離し、施設の長寿命化に対応する新たな仕組みづくりを早急に進めてほしい。
5.共同企業体による工事と総合評価落札方式適用工事における発注標準金額の引き上げについて【継続】
市内・中小建設業者向けに発注される工事のうち、特に上下水道局から発注される下水管きょ工事や水道施設工事では、予定価格が2億5,000万円未満の工事が数多く発注されており、業者が単体で入札に参加、落札することができる。予定価格が2億5,000万円をわずかでも超える工事の場合は、2者による共同企業体(JV)を組んで、入札に参加する必要がある。
近年、様々な物価が上昇しており、建設工事に係る資機材や労務費も大幅に上昇している。そのため、期せずして設計金額が上がってしまい、単体業者向けに通常の一般競争入札で発注されるはずであった工事、特に水道施設工事では、予定価格が2億5,000万円以上になり、総合評価落札方式適用工事ばかりが発注されるという状態になっている。
市内中小建設業者は、総合評価落札方式適用工事を受注できる可能性のある業者ばかりではない。水道施設工事を受注できず、工事実績を積み上げることができない状態が続けば、時間の経過とともに、工事を受注できる可能性はほとんどなくなってしまう。「2者JV」による工事の発注標準金額と「総合評価落札方式」の適用対象となる工事の発注標準金額については、物価の上昇に合わせた引き上げを要望する。
6.「災害時協定等締結団体」の会員業者に対する、入札参加資格におけるインセンティブについて【再要望】
令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)により川崎市内で発生した浸水被害の復旧作業は元より、直近では、令和6年の元日に発生した「能登半島地震」発生後、水道施設の復旧作業にも当たってきた。
毎年度、川崎市内各区の道路公園センターから数件発注されている「道路補修(緊急)工事」の入札参加資格においては、「主観評価項目制度実施要綱第2条(1)イ『災害時における本市との協力体制(災害協定)』又はウ『災害時における本市との協力体制(防災協力事業所)』に登録があること。」という条件が設定されており、防災協力事業所にのみ登録している業者と同列に扱われている。
防災協力事業所制度も重要であることは認識しており、(一社)川崎建設業協会会員業者の多くが登録している。せめて、「道路補修(緊急)工事」だけでも、「主観評価項目制度実施要綱第2条(1)イ『災害時における本市との協力体制(災害協定)』及びウ『災害時における本市との協力体制(防災協力事業所)』に登録があること。」という入札参加資格(条件)を設定した上で発注してほしい。
7.特に夜間工事の際に使用可能な「仮置場」の優先的な貸し出しについて【新規】
各区役所道路公園センターが管理する道路予定地は元より、川崎市各局が有している施設内の空き地や施設建設予定地等の市有地を、受注者が要望した場合には優先的に貸し出してほしい。
仮に貸し出しできないということであれば、当初設計において、仮置場に要すると見込まれる面積を拡大していただくとともに、単価を大幅に引き上げていただきますよう、要望する。現行の設計単価では、川崎市内のどの地域においても、仮置場として使用可能な空き地を賃借することはできず、結果的に、受注者が本来であれば得られるはずの利益を削って支出することになってしまう。
8.「余裕期間制度」の更なる拡大実施について【継続】
土木系の公共工事は、年度末に完成期限が設定されていることが多く、年度末近くになると、工事そのものは完成していても、設計変更や完成検査待ちにより、配置している技術者を外すことができず、新たな工事への入札参加を諦めざるを得ないケースがしばしば発生する。
令和6年4月以降は、建設業においても、労働時間の上限規制を遵守しなければならなくなった。現場への移動時間等も労働時間に含まれるため、1日の作業時間を従前よりも短縮せざるを得ない場合が増えている。現場における「週休2日制」を確保する必要のある工事も増えている。
令和6年度の第4四半期、「(発注者指定型の)余裕期間」が設定された工事が一定数発注されましたが、更なる拡大実施を要望する。第4四半期に発注される工事のすべてに「(発注者指定型の)余裕期間」を設定するとともに、適正な工期を設定した上で発注してほしい。「余裕期間」が設定されることにより、技術者・技能者(現場作業員)ともに、年度末にかけての人手不足を緩和でき、労働者の安全と心身の健康を確保できるようにもなる。
9.工期が複数年度にわたる工事の前払金について【継続】
工期が複数年度に渡る工事では、工事請負契約約款に、「債務負担行為に係る契約の特則」として、『各会計年度における支払限度額』と、『支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額』が定められている。前払金は通常、受注金額の約40%の金額を請求し、受け取ることができるが、年度ごとに支払限度額と出来高予定額が定められている場合は、その割合に基づいた前払金額しか請求できない。
その上、当年度に設定されている出来高予定額を明らかに上回り、中間検査(出来高検査)で合格しないことには、次年度に入っても、残りの前払金を請求することはできない。中間検査(出来高検査)受ける際に要する受注者の手間は、完成検査の場合と変わりがないため、結果的に残りの前払金を請求しないまま、完成を目指すケースが多くなる。
第4四半期、それも年度末近くに発注される工事で、仮に工期が10か月あり、当年度に2か月、次年度に8か月設定されている工事であれば、当年度に出来高予定額を設定せず、次年度に全額を設定する、あるいは、工期の長さ(月数)に基づき、当年度の出来高予定額を10分の2、次年度の出来高予定額を10分の8に設定するなど、受注者が前払金を請求しやすくなるような運用方法の見直しを要望する。
10.多種多様なインセンティブ発注の試行について【継続】
同札の入札者が発生した際に行われる「くじ引き」による落札者決定のプロセスでは、資材の調達や施工方法に係る受注者の創意工夫が反映されないという課題が生じていることを発注者として認識されている。
市内中小建設業者が受注機会を確保するための様々な施策が実施されていることについては、ありがたくいが、「くじ引き」の発生を抑制するために採用された「変動型最低制限価格」では、「くじ引き」が発生することはほとんどなくなったものの、『運』任せであることに変わりはなく、「くじ引き」と何ら変わりはない。入札参加資格に設定される条件は、公共工事における一般競争入札の性質上、「必要最低限」にしなければならないということは存じているが、総合評価落札方式が採用される案件における主観評価項目の条件設定には及ばずとも、市内業者の信頼性、社会性、地域性等に基づいて、様々な条件を設定することは、決して「必要最低限」を逸脱することにはならないと認識している。
市内中小建設業者の多くが一定数の工事を受注できるよう、多種多様なインセンティブを付した入札を『試行』してほしい。
市議団は、出された具体的な要望に対し、地元の中小企業の仕事を確保し、労働環境を守るため今後とも取り組むと述べました。