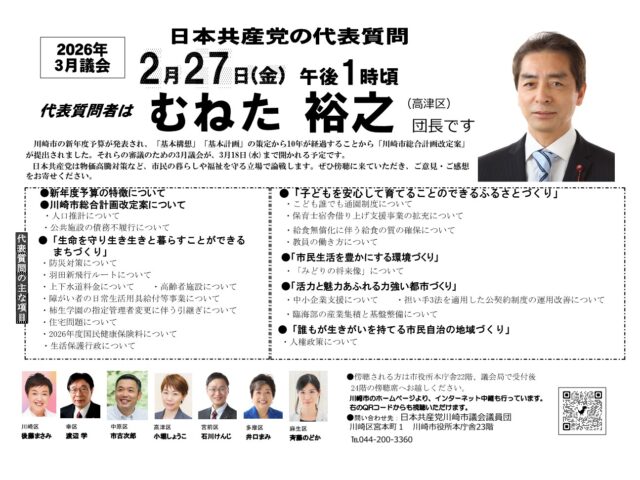2025年度第1回定例会で代表討論を行いました。
 2025年3月19日(水)井口真美副団長が予算案と諸議案について代表討論を行いました。日本共産党市議団は、予算案について、市民や中小企業には冷たく不要不急の大規模事業が進められており、「市民にとって極めて不公平な予算」と述べ予算案には反対しました。討論の全文は以下の通りです。
2025年3月19日(水)井口真美副団長が予算案と諸議案について代表討論を行いました。日本共産党市議団は、予算案について、市民や中小企業には冷たく不要不急の大規模事業が進められており、「市民にとって極めて不公平な予算」と述べ予算案には反対しました。討論の全文は以下の通りです。
2025年第1回川崎市議会定例会 日本共産党代表討論
2025年3月19日
井 口 真 美
私は日本共産党を代表して、今議会に提案された市長の施政方針並びに予算案を含めた諸議案について討論を行ないます。
新年度予算案の特徴についてです。
新年度一般会計予算の規模は、前年度比215億円増の8927億円で過去最大。市税収入も前年度比194億円増の4048億円で4年連続、過去最大で、財政力指数は、政令市トップです。財政健全化指標は、すべて基準値を下回っており、極めて優良。本市の人口は今後、増加し続けるため、市税収入の増加はかなりの期間続くと予想されます。ふるさと納税による減収はありますが、このように、市税収入、財政力指数、財政健全化指標のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持っています。
収支不足について、92億円のマイナスとしていますが、決算では、コロナ禍、一昨年度、昨年度とずっとプラスになっているのに、収支フレームをベースにしているため予算では毎回赤字を計上しています。予算は収支フレームをベースにするのではなく、直近の決算をベースに立てるべきです。
資産マネジメントについてです。
市は、「地域ごとの資産保有の最適化」と称して、集約・統廃合の対象となる施設を発表しました。わが党は、その問題点として、①人口減少を前提に「これ以上の床面積を増やさない」としていること、②不足している施設の対策がないこと、③市民にとってなくてはならない施設が統廃合される懸念があることなど3点を指摘しました。
特に、人口減少を前提に「床面積を増やさない」という方針についてですが、市民一人当たりの床面積は、政令市の下から4番目で、今でさえ少ないのです。人口については、これから人口増加が続き、今よりも人口が減るのは、30年後です。そうなると現在、平均倍率が10倍以上の市営住宅、待機者が2000人以上の特養ホームなどは、さらに不足して耐え難い状況が30年間続くことになり、自治体としての責務を放棄することになります。人口減少を前提に「床面積を増やさない」という方針は間違いであり見直して、不足している施設の増設を求めます。
子育て支援策についてです。
子育ての経済的負担の軽減について、市長は「国がやるべき」との答弁を繰り返しました。しかし他の自治体は国がやらないからこそ、独自に支援に踏み出しているのです。多摩川格差は保護者にとって看過できない状況になっています。住民の福祉の増進を図る役割のある自治体の長として、小児医療費の18歳までの完全無償化、保育料の引き下げなどを実施するよう、要望します。
教員不足についてです。
2月1日時点の教員未充足は205.5名に上りました。再三にわたり私達が求めて来た定数内欠員を正規の教員で確保する方針変更を行なったとの答弁もありました。しかし、採用試験を3回行なっても冬期採用の応募人数は募集60名程度に対し33名という結果です。学校プールの水流出事故による直接請求をはじめ、特別休暇を不正取得したとする給与返納、遅れをとっていたハラスメント対策等、現場を大切にせず一方的な処分を重ねる環境に人は集まるでしょうか。現場に寄り添った市教委の姿勢の対応に改めることを求めておきます。
高圧ケーブルについてです。
市が所有する7施設で計9回の高圧ケーブルによる停電が発生しています。2月に発生したはるひの小中学校は2カ月前に年次保守点検を行っており、年次点検では止められないことも改めて明らかとなりました。漏電、感電の恐れもある高圧ケーブルの相次ぐ絶縁不良が子ども達のいる学校で多発している状況を重く受け止め、該当ケーブルの速やかな交換、国への報告、メーカーへは責任ある対応を求める協議の継続を要望します。
障がい者の日常生活用具給付等事業についてです。
物価高騰で日常生活用具も価格高騰し、購入が困難になっている、そして今の給付上限額は2013年10月に改定され、11年も経っている、と指摘し、なぜ引き上げを行わないのか伺いましたが、基準額を超えていることは認識しているが、引き上げなどについて慎重に検討、との答弁でした。
物価高騰対策は他の施策では、様々行っています。障がい者が日常の暮らしに必要だから給付している用具だけ11年前のままというのは、障がい者を取り残す事になるのではないでしょうか。給付上限額の引き上げを強く要望します。
視覚障害者の皆さんは具体的に要望を出し、市との建設的な対話を求めています。答弁にあったように、これまでと同様に、という姿勢は障害者差別解消法にも反するものです。この姿勢をいつまで続けるつもりでしょうか。これまでと同様、ではなく、障がい者の権利を保障し建設的対話を行うよう要望します。
特別養護老人ホームの増設についてです。
第9期かわさきいきいき長寿プランおいて、なぜ新規建設整備だけが計画されていないのかとの質問に対し、ショートステイからの転換や既存施設の増築による296床の増床で足りるため、との本市の考えが示されました。また「2040年までの必要整備数753床」とする根拠については「高齢者実態調査の結果や、要支援・要介護認定数の推計値等を踏まえている」とのことです。
本市は常に2000人以上の待機者がいます。15年で753床増床の計画では足りません。必要な方が入所できるよう新規建設整備も計画に入れた増床を促進して公的責任を果たすよう要望します。
2025年度国民健康保険料についてです。
他の健康保険の2倍の高すぎる国保料を軽減するために、一般会計からの繰入を増額するように求めました。しかし、国から一般会計からの法定外繰入は、早期解消を求められている。現在、段階的な縮減を図っている、増額は困難と拒否した答弁でした。また、県内他自治体が子育て世帯の負担軽減として実施している、18才までの均等割の減免を求めましたが、制度主体である国の責務で実施すべきと認識している。と本市では実施しないと、これまでの答弁の繰り返しでした。物価高騰、年金実質引下げが続く中で、さらに国保料の値上げは生活を困難にしています。国保料の値上げは止め、子育て支援の18才までの均等割の減免を行い、軽減化を図ることをひき続き求めます。
中小企業支援についてです。
中小企業支援事業の関連予算は、一般会計の僅か0.17%に過ぎず、抜本的な増額が必要と求めたのに対し、市長の答弁は「経営基盤が図られるよう、国の交付金等も有効に活用しながら、必要な予算を配分する」とのことでした。しかし、補正予算も市独自の上乗せはなく、本予算も含め、材料費の高騰や円高など、苦境に立たされている市内事業者を支えるには、全く不十分なものでした。改めて仕事確保のため、事業のマッチングを図るためのコーディネーターの増員、電気料金の値上げや家賃の支払いなどに困っている事業者への固定費補助、人材確保のための奨学金返還支援制度の拡充、住宅リフォーム制度の創設、商店街街路灯への補助金の引き上げなどの対策を講じるよう求めておきます。
等々力緑地再編整備についてです。
633億円から1232億円に上る事業費の倍増は契約106条に明記されている「不可抗力による解除」に該当しないのかと代表質問で質したのに対し「地震等の自然災害や火災等の人為的災害、大規模な感染症等を定義しており、該当しない」という答弁でした。つまり、一度PFIという形で契約を結んでしまえば、自然災害等が発生しない限り、事業費が膨れ上がろうと容易に後戻りできないということです。事業費縮減を主たる目的とするPFI事業がいかに矛盾をはらみ、市民おきざりの手法で進められていくという実態が改めて明らかとなりました。この事実を重く受け止め、PFI手法ありきの政策方針を改めることを求めておきます。また多くの樹木を伐採し、市民の憩いのスペースを奪い、事業者の利益優先となっている現等々力緑地再編整備計画の縮小、見直しも重ねて求めておきます。
市営住宅についてです。
本市の平均応募倍率は約10倍です。川崎区では、全市平均の約4倍、5倍に達し、最高倍率は約100倍が続いていることを、質疑の中で明らかにしました。「供給が不足している」と指摘をしたところ、「民間賃貸住宅を活用した取り組みを進めるが、新規住宅の建設予定はない」との答弁でした。住宅生活基本法第6条では「憲法に基づく人権条項に従い、住宅確保の施策を行わなければならない」としています。新規整備計画を策定し、抜本的に増やすよう求めます。
また、長寿命化改善事業や漏水事故改善事業などで募集を停止している政策空家は、計画を前倒しし、早急に募集を行い、ストックの有効活用を促進するよう要望いたします。
南武線駅アクセス向上等整備事業についてです。
橋上駅舎化について、中野島駅と久地駅が残っています。
久地踏切はピーク時の遮断時間が1時間のうち40分以上の開かずの踏切で、久地駅橋上駅舎化を求める5千筆の署名も川崎市に届けられている、それなのに今回も予算がなにもついておらず、どうなっているのか質しましたが、相変わらずの答弁でした。
一方、危険な久地駅を残したまま、南武線のワンマン運転が始まりました。川崎市は乗客である市民の安全を守る責任がある、JRに南武線のワンマン運転は行うべきではないと言うべき、と求めましたが、JRの責任で適切に実施するもの、との答弁でした。踏切の安全のためにも、乗客の安全のためにも、本市は動きません。改めて、南武線駅アクセス向上等整備事業を進める事と、ワンマン運転の中止をJRに申し入れるよう強く求めます。
防災対策についてです。
震災対策のかなめである、木造住宅耐震改修助成制度が、助成額と助成件数を増やしているとはいえ、まだ不十分だとして、拡大を求めましたが、「今後の申請状況を注視していく」とのことです。代表質問で指摘したように、能登半島地震をうけて市民は関心を高め、耐震診断士派遣制度の活用は今年度大きく増えています。しかし、診断を受けた人たちが改修まで至らない最大の原因は費用の大きさ、つまり「そんなにお金がかかるならできない」ということです。ここに大きく支援を入れなければ改修は進まないことを強く指摘し、補助額と補助件数の抜本的な増を求めておきます。
予算案全体の特徴として、市税収入は過去最大、財政力はトップなのに、社会保障費は平均以下、学校給食費や子ども医療費など東京との「多摩川格差」だけでなく県内との格差も広がっており、2000人の待機者がいる特養ホームは一切新設せず、中小企業の予算はわずか16億円で全体の0.2%しかないなど、市民や中小企業には冷たい予算となっています。一方で、臨海部では、事業費が当初の約4倍、1950億円となった臨港道路東扇島水江町線など不要不急の大規模事業がすすめられ、海外水素の見通しがつかない水素戦略やJFE跡地利用に今後、2000億円も支出するなど、市民にとって、きわめて不公平な予算となっています。
一方、川崎市は大きな可能性を持っています。減債基金は、他政令市と比べると1.6倍、700億円も多い残高となっています。この減債基金への積立額を減らして、政令市トップの財政力を市民のために使えば、日本トップクラスの福祉施策が実現できます。不要不急の大規模事業は中止・凍結し、政令市トップの財政力と各種基金を市民の福祉・くらしのために使うことを要望します。
議案第5号 川崎市特別職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてです。
市長及び副市長の給料の額を引き上げる改定を行うための改正です。現在でも高い額ですのでこの議案には反対です。
議案第6号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてです。
この議案は、雇用保険法の一部改正に伴い、失業者の退職手当のうち就業促進手当に相当する退職手当の支給要件を改めること等のために改正するものです。
この法改正により、就業促進手当のうち、就業手当が廃止されました。就業手当というのは、非正規で再雇用する場合、就業後も失業手当の30%を支給残日数分給付し、就業後の賃金を補填する制度ですが、今回の改定で、この就業手当がなくなってしまいます。
この法改定自体、雇用保険制度そのものを一層低賃金、不安定雇用を促進する手段にしてしまうということで、わが党は反対してきました。よって、この議案には反対です。
議案第7号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定についてです。
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律による行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正」に伴い引用条文の規程の整備を行うものです。
改正法では、法人・不動産登記のデータと住所・所在地関係のデータに関する公的基礎情報データベースの整備について個人情報を匿名加工していれば本人の同意なしに目的外流用が可能となります。プライバシー保護が疎かな現行制度のもとで民間企業等による利活用を進めることは認められないためなどから本条例には反対です。
議案第10号 川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 堤根余熱利用市民施設整備事業の契約の締結について、議案第49号 川崎市堤根余熱利用市民施設の指定管理者の指定についてです。
議案第10号では、堤根余熱利用市民施設を条例に位置付けるとともに、利用料の設定を行い、議案48号ではPFI手法による整備の契約について、議案第49号では、指定管理者の指定について、それぞれ、提案されているものです。
PFI事業の手法は、民間資金、技術などを使い公共施設の整備を進めるもので、公共分野の仕事を広く民間の事業に明け渡すものとして、反対しているものです。
今回の案件は、市の管理・監督責任も確認でき、早期整備を望む住民の声もあることから、議案第10号、議案第48号、議案第49号については賛成をし、今後の推移を見守ることとします。
議案第26号 川崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
本議案は、地域包括支援センターの職員配置の改正です。地域包括支援センターに必置とされている常勤の3職種である保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の職員確保が困難な場合は、職員の勤務延べ時間数を満たせば常勤でなくても可能とする。また、複数のセンターが担当する区域を一の区域として常勤職員数が基準を満たした場合は、一つのセンターで3職種の内、2職種とすることを可能とするものです。
この改正は規制緩和であり、高齢者の総合相談、支援業務をチームとして継続し行うことに支障が出る懸念があり、高齢者サービスの低下と常勤職員に過重な負担を掛けるものす。必要なことは、現行でも業務多忙な職員配置基準を増員し、人材確保と定着を図る必要があることから、本議案には賛成できません。
議案第36号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてです。
この議案は、条例第4条の公園における禁止行為の中に「喫煙」を加えるものです。これにより、指定された場所以外での喫煙をしたものは、28条が適用され5万円以下の過料が課されることになります。
公園を受動喫煙もなく安全で快適にするのは当然のことです。問題はそれを過料という罰則で規制することです。行政が公権力を使って市民を罰するにはそれ相応の理由と市民合意が必要です。本当に罰則を適用して市民を律するなら、誰がどうやってどんな手順で過料を科すのかを慎重かつ明確に示す必要がありますが、そのフローはこれから作成するとのことで、市内1200もの対象公園で実効性があるのか、全く不透明です。
わが党は罰則で禁煙を強要することは反対です。委員会でも審議されたように、必要なのは、広く市民に喫煙についての認識を広げ、マナーを守ることで受動喫煙などを防ぐことだと考えます。公園においても喫煙を減らすために市民へ徹底した啓発を行い、公園では吸わないという市民合意を作ることが何より大事であり、市民を罰則で規制する条例改正には反対です。
議案第45号 大師地区複合施設の建物の取得についてです。
「身近な地域の拠点」をとして設置される大師コミュニティセンターは市民に求められていることですが、その前提として行われたこども文化センター及び老人いこいの家の条例からの削除、廃止はそれぞれの目的や独自性を失いかねません。以上のことから本議案には反対です。
議案第52号 中央療育センターの指定管理者の指定についてです。
当該施設の指定管理者に社会福祉法人同愛会を指定するものですが、私たちは当初から指定管理者制度の導入に反対してきました。
中央療育センターは障がいを持つ子どものための施設で、質を担保するには職員の知識や経験の積み上げや、利用者との信頼関係の構築が必須です。指定管理者が選定される度に、これらの必須のものが失われるリスクを負うべきではありません。
さらに、市の権限やノウハウの損失も重大です。指定管理者が問題を起こしても、市はそのすべてにおいて権限を有しているわけではありません。調査や改善を図るにしても相手との調整をしなければならず、そのプロセスは複雑化します。直営の施設だったらすぐにできることが、指定管理者の施設ではできなくなるのです。当該施設で死亡事故が起きてからの対応の遅さや不十分さは、こうした指定管理者制度のデメリットが一因になっています。
また、委員会の議論では、療育センターに勤めた経験のある市職員がまだいるという答弁もありましたが、いずれかはゼロになります。そうなったときに、施設の監督や監視、あるいはどのように発展させていくのかといった政策的な判断をするだけのノウハウが川崎市に残っているでしょうか。
当該施設は指定管理者制度には馴染みません。直営に戻すことを改めて要望し、本議案への反対を表明します。
議案第66号 令和7年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算についてです。
高齢者に差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から賛成できません。
議案第80号 2024年度川崎市一般会計補正予算についてです。
この補正予算には、臨港道路東扇島水江町線の建設費用の分担金、19億6千万円余が含まれていますが、教育・福祉・建設分野などで、必要な予算も多く含まれていることから、議案第80号には賛成します。
議案第83号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第84号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これらの議案は、地域型保育事業に必要な保育内容についての支援や代替保育のための連携施設の確保等の見直し、及び卒園後の受け皿も含めた連携施設の確保をについて、さらに5年間猶予を延長するものです。
この基準緩和は保育連携において小規模保育事業者への負担増、代替保育においては休園となり保育の継続が絶たれるばかりか、家庭的保育者が体調を崩しても安心して休むことができない状況に陥ることとなります。本市は現状で保育連携、代替保育については連携施設を確保しているわけですから、国の基準緩和に準ずるのではなく本市独自の基準を設けるべきと考えますので本議案には賛成できません。
議案第85号 令和7年度川崎市一般会計補正予算(当初補正)についてです。
本補正予算の内、福祉施設等物価高騰対策事業費についてです。物価の値上がりが続いているのに、なぜ福祉施設等へのひと月当たりの給付額が、前回、令和6年9月補正の2分の1程度なのかと質しました。答弁は、給付額の算出を県の基準である、2分の1に合わせた、との答弁でした。原資は国庫補助金と県補助金のみで、本市の支出はありません。物価高騰が、福祉を支える高齢者、障がい者施設の運営を厳しくしておりその対策として給付するもので、不十分です。本補正は、他の事業の必要な予算が含まれていることから賛成しますが、物価高騰分の今回の給付額の不足分を、本市が早急に補填することを求めておきます。
議案第87号 川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について、議案第88号川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第89号 川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これらの議案はこども家庭庁が進める乳児等通園支援事業、通称「こども誰でも通園制度」の本格実施に向けて制度化を行うための条例の制定及び改正です。本市は先んじて試行的実施を行い、アンケートやパブリックコメントを行いましたが、利用時間の短さや補助金の不足、保育現場からの負担増に関する意見が寄せられていたにもかかわらず、適正性についての検証を続けるだけで、ほぼ国の基準に従って制度を実施するとのことです。条例案第24条では保育指針に基づいた支援を提供することが求められていますが、保育現場や利用者からの改善要望に対して何の対応もせずに制度を実施することは、「子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」という保育指針に沿った保育を提供することは不可能です。国の責任は重大であると考えますが、国の誤った政策から川崎の子どもたち、その家族、保育現場を守ることが自治体の責務です。その責務を放棄しようとする議案には賛同できません。
請願第22号 歩道における車両乗入部の平坦化を求める請願、 請願第23号 排水口(溝)の蓋の取替えを求める請願、請願第24号 歩道における縦断勾配の緩和を求める請願、 請願第25号 横断歩道滞留部分(歩道だまり)等の平坦化を求める請願、請願第26号 視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置と維持管理を求める請願についてです。
いずれも、市内の歩道における歩行者の安全対策が整っていないところが多く、国の基準などからも逸脱している個所もあるとして、その整備を求めているものです。審議の中で、指摘される個所についてすでに改善したところや、今後の改善計画を持つなど、市として対処する姿勢があることがわかりました。なかには大規模な改修が必要で今すぐできないところもありますが、それも今後既存不適格などで改善されていく道もあります。市民が安全に歩道を利用できるようにすることを求めることが大きな趣旨であり、これは市全体で目指すべきものであり、趣旨採択するべきです。
以上の立場と予算組み替えとの関係から日本共産党は、議案第5号~7号、議案第26号、議案第36号、議案第45号、議案第52号、議案第61号、議案第62号、議案第64号、議案第66号、議案第68号、議案第69号、議案第73号、議案第83号、議案第84号、議案第87号~89号に反対し、その他の議案、報告、請願については賛成及び同意することを表明して討論を終わります。