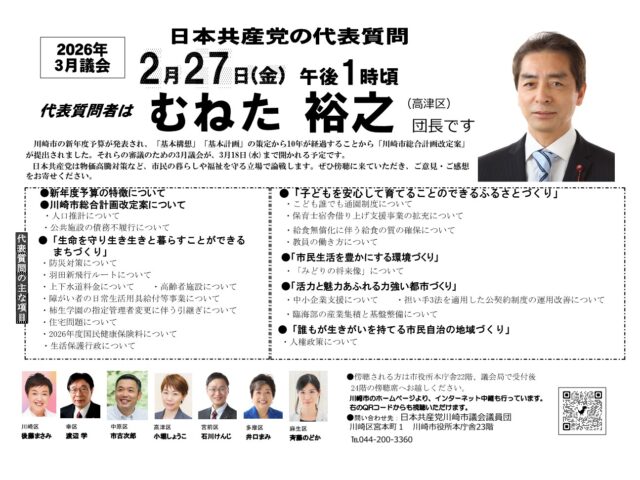2025年第3回定例会で市古次郎議員が代表質問を行いました
日本共産党代表質問(初回質問)
日本共産党 市古 次郎
私は、日本共産党を代表して2025年第3回定例会に提案された諸議案、ならびに市政一般について質問を行ないます。
核兵器廃絶についてです。
市長は8月9日、長崎の原爆の日に、平和祈念式典に参加され平和首長会議の被爆80周年記念総会に出席されたとのことです。平和首長会議はこの日、国内加盟都市会議において「核兵器廃絶に向けた取組の推進について」と題する石破総理大臣あての要請文書を採択しました。市長もその場におられたことと思います。要請書では、核兵器が使用されるかもしれないという重大な情勢のもと「国レベルの平和への取り組みをボトムアップで支え、核兵器廃絶に向けた動きを後押ししたい」として、「一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批准」することを求めています。この要請書を採択した一人として市長の思い、見解を伺います。
2024年度決算の特徴についてです。
2024年度一般会計決算では、歳入総額が8713億円、歳出総額が8622億円となり、実質収支額はプラス65億円の黒字となりました。市税収入は、30億円増の3909億円で3年連続、過去最高となり、これは固定資産税が28億円増、法人市民税も企業収益の増により25億円増などによるものです。財政力指数は、政令市で唯一、1を超え、基準財政収入額が需要額を上回っており、政令市トップを続けています。そのため政令市で唯一の普通交付税の不交付団体となっています。財政健全化指標は、すべて基準値を下回っており、極めて優良。一人当たりの市債残高は、政令市の平均よりも9万円低く、借金の負担額が少ないのが特徴です。川崎市は、政令市で平均年齢が最も若く、生産年齢人口割合が最も大きい都市で、人口推計でも今後10年間は増加を続けるため市税収入の増加は今後10年続くと予想されます。このように、市税収入、財政力指数、財政健全化指標のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持っています。
収支フレームについてです。
24年度予算では157億円の収支不足が出るとしていましたが、決算では65億円のプラスとなりました。収支不足をなんと220億円以上も過大に試算していました。わが党は、予算、決算議会で何度も収支不足額が過大であると主張してきましたが、またまたその通りになりました。24年度の収支不足額ついて、なぜ、これだけの誤差が生じたのか、伺います。誤差の原因は収支フレームにあります。今後もこの収支フレームに沿って予算を立てれば、過大な収支不足額のために必要な予算が取れなくなります。これだけの誤差が出ている収支フレームは、他の自治体のように、毎年、決算をベースに見直しをして実態に沿ったものにすべきです、市長に伺います。
減債基金についてです。
24年度予算では減債基金から157億円借入れる予定でしたが、決算では収支不足が出なかったために借入はゼロとなりました。減債基金残高は、一般会計分でみると積立額488億円、取崩額314億円で2940億円となり、一人当たりの残高は政令市平均の1.6倍にもなります。政令市の減債基金残高は、多くが取崩額の平均4年分ですが、本市の場合は8年分にもなります。減債基金からの借入507億円を差し引いた実質残高は2433億円ですが、取崩額4年分を差し引いても約1000億円も多く、他都市と比べて極めて多い残高となっています。こんなに貯める必要はありません。他都市のように残高を取崩額4年分にすれば、市民のために1000億円は使えます。
物価高騰などで市民生活・中小企業の経営が大変になっています。だからこそ、減債基金の積立額を減らして市民生活・中小企業支援に回すべきです、市長に伺います。
社会保障費と個人市民税についてです。
社会保障費である一人当たりの扶助費の額は、政令市の平均を下回っており、福祉予算である民生費も政令市平均よりも約2万円低い状況です。一方、個人市民税は、政令市平均より約3万円高く、政令市トップです。東京23区の住民税平均よりも高いのです。個人市民税は全国で最も高いのに、その税収が福祉・暮らしには十分還元されていないのではないか、市長に伺います。
特別市についてです。
川崎市は、指定都市制度の問題点について、「指定都市と道府県の「二重行政」の存在と「不十分な税制上の措置」という課題がある」としています。市はこれらの課題解決のために「川崎市が原則として県の仕事をすべて担い、権限と財源を市に一本化」し、「二重行政を解消し市民サービスが向上するとともに、県を通さず国と直接やり取りすることで、素早い対応が可能になる」として特別市をめざすとしています。これに対して神奈川県は、21年11月「特別自治市報告書」を発表し、最近はパンフレットも作成して、様々な角度から反論を述べています。
市が指摘する指定都市の課題の一つである「二重行政」についてです。
国で地方自治法が改正され、すでに都道府県から指定都市へほとんどの事務・権限が委譲されています。県は、二重行政について、これまでのように「個別具体的な支障があれば、指定都市都道府県調整会議を活用して、施策の見直しや事務・権限の移譲等を行うことなど、具体的な解決を図るべきである」としています。この間、この手順で県費負担だった教職員の給与負担を市に移譲しています。市は幼稚園の窓口や信号機の設置などを二重行政の例として挙げていますが、個別に対応すればよいだけの話ではないですか、市長の見解を伺います。
課題の2つ目「税制上の不十分な措置」についてです。
県の報告書では「地方自治体全体が財源不足の中で、道府県・指定都市間の税源の奪い合いでは、根本的な解決にならない」と述べ、「地方税財政制度は国の法律によるものであり、本来の仕事量に応じた税財源は国に求めるべきである」と主張しています。全くその通りだと思いますが、市長の見解を伺います。
さらに県の報告書では様々な問題点を指摘しています。
県の総合調整機能・広域行政についてです。
県は、医療、警察など、県内に偏在する地域資源を有効活用し、広域的なスケールメリットを活かした取組や、市町村のバックアップといった取組を展開するなど、県内全域で「総合調整機能」を発揮しています。この機能が特別市になると、「こうした県の「総合調整機能」に大きな支障が生じ、指定都市域を含む住民サービスが低下するおそれがある」と指摘しています。
例えば、コロナ禍で川崎市は市内の病床が不足し満床状態となりましたが、県が入院・搬送調整をして、県内の病院に1987人もの患者を受け入れてくれました。こういう感染症病床や精神病床の不足をどうするのか、医療提供体制にしても、今まで県が担っていた高度・特殊な専門的医療などはどうするのかという問題もあります。警察については、「県境を越えた広域事案」をどうするのか、また、今まで県が担っていた警察本部、鑑識課、科学捜査研究所などの施設や警察官・職員は自前で持つのか、という問題もあります。これらの県の総合調整機能をどうやって特別市で実現していくのか、市長の見解を伺います。
県民・市民の負担についてです。
現在、市内の県有施設は134施設あり、財産価格1622億円にもなります。特別市側は県有施設の移管・取得費用や債務引き受け額などは相当な額になると思われます。また、市が新たに整備する必要がある機関・施設もあります。公安委員会、労働委員会、警察本部など、これらの機関については、専門的な業務を担うため、専門人材の育成・配置などの新たなコストも生じてきます。
さらに、特別市になれば、これまで県が担っていた事業を市が負担するようになります。例えば、警察・交通機能の維持管理・運営費用、道路や河川の維持管理・改修費用、県有施設の維持管理、県営住宅、学校などの長期修繕費用などです。これらの莫大な費用の財源はどのように確保するのか、市長に伺います。
県や市の財政面の影響についてです。
神奈川県の県税は、約6割が指定都市域から入っています。県の報告書では「仮に全ての県内指定都市が特別自治市に移行した場合は、県の財源不足は約680 億円となり、この不足額は県の政策的経費の3分の1に相当し」、これが失われれば「指定都市以外の県内市町村域では、県の行政サービスの水準維持が困難となるだけではなく、災害対応、新感染症等対策、水源環境保全・再生といった県の総合調整機能にも影響が及ぶものと考えられる」としています。このように財源不足によって県民サービスの維持に困難をもたらすことについて、市長の見解を伺います。
指定都市にとっても、特別市になれば、財産価値1600億円の県有施設の取得費用や維持管理、修繕費用など莫大な財源が必要になります。特別市になって県税を納めなくなったとしても、これらの支出が増えるために、逆に財政面でもマイナスになる可能性があると思いますが、市長に見解を伺います。
子育て支援についてです。
小児医療費助成制度についてです。
市長は8月25日の記者会見で対象を18歳まで拡大し、一部負担金を撤廃する方針を述べられました。子ども達の医療費に支援を求める市民からの陳情、請願は議員図書館で確認できる限り1988年まで遡ります。それから37年間、93年には10万筆を超える請願をはじめ、0から2歳、就学前、低学年、小学生、中学生、そして18歳までと繰り返し拡充を求める声が届き続けた中、ついに7月の文教委員会において、18歳まで無料化を求める陳情が趣旨採択となりました。絶え間ない市民の声が市政を動かしたことは紛れもない事実であり、陳情趣旨に則った方針を打ち出した点は歓迎するところです。しかし、記者会見の場ではこの選択を「苦渋の選択」と表現していました。その様子を伝えた記事には「子どもの為に使う13億円は苦渋の決断なんだ?」「苦渋の決断ておかしくない?」といったコメントが寄せられています。苦渋とは「物事が重い通りいかず苦しくつらい思い」という意味合いとなりますが、市民の多くの要望にそのような表現をすることは、首長の姿勢として不適切ではないでしょうか。伺います。
13.7億円の財源については他の子育て予算から付け替え、削減などあってはなりません。他の福祉予算から付け替えなくても充分捻出できます。財政局長の見解を伺います。
拡充時期についてです。
文教委員会で示されたスケジュールでは9月からの制度拡充となっていますが遅すぎます。一日でも早く制度拡充を行うべきです。伺います。
やむを得ず9月からの制度拡充となってしまった場合、最低でも来年3月で経過措置が終了する小児ぜん息医療費支給事業は特例を設け、8月まで医療費の支給を延長するべきです。伺います。
多摩川格差について、市長に伺います。
東京都は今月から保育園利用料が0歳から無料になりました。学校給食もすでに小学校、中学校ともに無料です。川崎市では、年収600万円から700万円の世帯が子どもを2人育てた場合、0歳から2歳までの保育園利用料と、公立小中学校の給食費で合わせて385万円もかかります。それが、東京であれば0円なのです。さらに東京都は018サポートといって0歳から18歳まで子どもひとりあたり月5,000円給付しており、子ども2人で計200万円ほどもらうことができます。私立の高校授業料も、東京都は所得制限なしで無償となっています。
市長は8月25日の記者会見で「多摩川格差という言葉自体が非常につくられた、誘導するような言葉で、状況をまったく表していないと思う」と発言をしていましたが、多摩川格差は本市で子育てしている人にとっては現実問題だという認識はあるのか、伺います。
また市民は保育園利用料の引き下げや学校給食の無償化など、市としてできる経済的負担の軽減は積極的にやってほしいと望んでいます。市長はその望みに応えるのか、伺います。
わくわくプラザについてです。
「放課後等の子どもの居場所に関する今後の方向性」に関する中間報告のなかで、わくわくプラザに区分制を導入する案が示されました。放課後児童健全育成事業をわくわくプラザのA区分、それ以外の全児童対策をB区分として分けるとのことです。A区分の子どもはひとりあたり1.65平米の専用区画を確保するものの、プラザ室だけで面積が足りなければ空き教室も活用すると委員会で説明がありました。
放課後児童健全育成事業は子どもに生活の場を提供するもので、国の運営指針やその解説書にも生活の場としてふさわしい環境を整えることの重要性が強調されています。これらを鑑みると、わくわくプラザA区分は空き教室には頼らずに、定員を決めたうえで既存のプラザ室のみで実施すべきですが、なぜそうしないのか伺います。
熱中症対策こどもの遊びの保障についてです。
気象庁は、今年の夏の全国の平均気温は平年より2.36度高く、統計のある1898年以降で最も暑かったと発表しました。
保育園や学校では、熱中症対策として、暑さ指数を測定し「危険」WBGT 31℃以上の時は、外遊び、プールは中止となります。外で身体を動かして遊ぶ事は、こどもの心と身体の発達のために必要な事です。夏休み中など学校等施設以外のこどもの遊び場が必要です。こどもたちが毎日身体を動かし汗をかいて遊ぶ、動的な遊びができる事を保障するべきです。
横浜市には、各区にこどもログハウスという施設があり、ログハウスの中には、らせん滑り台、地下迷路、ネット登りなどの遊具があり、こどもたちが楽しく身体を動かして遊ぶことができます。 川崎市でも、暑さの中でも、こどもの動的な遊びを保障できるよう、横浜市のように各区にこどもログハウスを作るべきです。伺います。
ひとり親家庭への支援についてです。
来年に予定をしている「子ども・若者の未来応援プラン」の改定にあわせ、物価高騰の影響下にあるひとり親家庭の状況やニーズを把握し、改定策定にむけた参考資料として活用することを目的としたアンケート結果が公表されました。
6142件に配布し2475件から回答があり94%が母子家庭です。90%が就労していますが約半分がパート、アルバイトなどの非正規雇用、額面年収は200万から300万未満が最も高く、多くの方が中学生から高校生の子どもを育てている実態が浮き彫りになりました。「食べ盛りのこどもが2人いるが急激な物価上昇で、特にお米が高くて買えない」「給食費を無償に」「母子家庭への住居助成金が欲しい」など本市施策に関する意見は484件も寄せられました。「なんとかしてほしい」との声に応え、自立を支えるためにも財政支援を強化する施策を改定時の応援プランに盛り込むべきです。伺います。
特に、民間賃貸住宅に居住する方が45.4%と最も多く、家賃も含む住居費は7万円から10万円未満です。年収が300万円未満に対し、住居費の負担はあまりにも重すぎます。杉並区は区営住宅に落選したひとり親家庭世帯などに家賃補助施策を開始しました。杉並区のように家賃補助施策を創設し支援すべきです。伺います。
教育をめぐる環境整備についてです。
いじめ重大事態調査についてです。
本市が行っている「令和5年度川崎市立小中学校における児童生徒の問題行動・不登校等の調査結果」によると、本市のいじめ認知件数は増加の一途をたどっています。「いじめ」はいかなる形をとろうとも人権侵害であることの認識に立ち、速やかな子ども達への寄り添った対応、実効性のある確実な再発防止が求められます。その対応を着実に行うためにも重要なのが、いじめ防止対策推進法に基づくいじめ重大事態調査です。調査に関するガイドラインによると「重大事態とは、いじめにより重大な被害が生じた、疑い又は、いじめにより不登校を余儀なくされている段階を指し、これらの疑いが生じた段階から調査の実施に向けた取組を開始する」と明記されています。報道によると、横浜市では市立中2年の女子生徒がいじめを苦に自死した事案で調査の着手が遅れたことを踏まえ、徹底した再調査を実施したところ重大事態案件が59件、確認されたとのことです。一方で本市の24年度から過去5年間の重大事態認定件数は3件です。あまりにも少なすぎると思いますが、本市ではガイドラインに基づいた確実な重大事態調査が行われているのか伺います。
児童生徒・保護者からの申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたるとガイドラインに規定されていますが、23年度は過去最高の5472件のいじめ認知件数があったにも関わらず重大事態案件は0件です。23年度は児童生徒・保護者からの申し立ては一切なかったのか、若しくは法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかであるという理解でよいのか伺います。
昨年8月に国のガイドラインが改定されていますが、本市の「川崎市いじめ防止基本方針」は2022年4月に改訂されたのが最後で、重大事態への対処の部分には改定内容が反映されていません。その理由を伺います。
ガイドラインの改定が反映されないまま、現在まで重大事態の対応を行ってきたのであれば、すぐに改めるべきです。横浜市のように再調査の検討も含め今後の対応を伺います。
重大事態案件の対応は学校と教育委員会が連携して対応するとされていますが、横浜市は再調査実施後、教育現場への負担軽減、再発防止、なにより速やかな子どもの救済のために、今年度いじめ対応専門の教育主事を12名増員し対応にあたっているとのことです。本市も専門の人員を増員、確保し、いじめ防止対策にあたるべきです。伺います。
学校給食室への空調設置についてです。
市教委が昨年7月に実施した「給食室における室温状況調査」によれば、空調が未設置の給食室では室温が50度に達する状況が確認されました。また、調査に協力した79校の中で、労働安全衛生規則の改正に伴う熱中症対策の義務付け対象となる気温31度以上の給食室は52校に達しています。一方、空調が設置されている27校では、ほとんどの給食室で平均室温が30度以下となっています。これはあくまで平均室温であり、火を使用している状況では体感温度はさらに高く、調理員の方々にとって熱中症の危険が常に存在する職場環境であることが容易に想像できます。給食室への早急な空調設置が求められていますが、過去の答弁では「増改築等の機会に合わせて設置していく」と繰り返し述べています。それでは遅すぎます。今期、久地小学校と富士見台小学校で空調設置の実証実験が行われているとのことですが、すぐに効果測定を行い、早急に全ての給食室へ空調設置を進めるべきです。伺います。
体育館への空調設置についてです。
8月27日の文教委員会での整備方針の検討状況では、PFI手法での検討を進める方向性が示されましたが、PFIでは地域経済の活性化が図られないばかりか、事業者選定や設計に時間がかかり、工事着手までに最低2年は必要です。市が行ったサウンディング調査でも「従来手法は速やかに施工に着手できる」との意見がある通り、早期設置を最優先に考えるなら、従来手法での発注が最適です。従来手法での整備を進めるべきです。伺います。
実際に早期設置に取り組んでいる横浜市や千葉市も一般競争入札で工事に着手しており、PFI手法などは採用していません。PFIの方が早期設置できるという根拠について伺います。
また、空調が設置されるまでの間、大型冷風機やスポットクーラーを稼働させるとブレーカーが落ちて使用不能になるという声が複数届いています。体育館の電気容量を増やすべきです。伺います。
議案第141号川崎市多摩市民館の指定管理者の指定について及び議案第142号川崎市麻生市民館、川崎市麻生市民館岡上分館、川崎市立麻生図書館及び川崎市立麻生図書館柿生分館の指定管理者の指定についてです。
社会教育施設の運営には、施設や職員の専門性や継続性が必要不可欠です。しかし指定管理者制度のもとでは経費縮減のために人件費が削られ、その専門性や継続性が担保できなくなる恐れがあると私たちは指摘をしてきました。各議案により、どれほどの経費縮減が見込まれるのか、伺います。
人権にかかわる施策についてです。
「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」についてです。
7月に行われた参議院選挙期間中に外国人差別や分断をあおる主張が公然と行われました。子どもを持つ外国にルーツのある本市住民の方からは「外国人バッシングが怖くて怖くてたまらない。守ってほしい」と不安と悔しさが入り混じった声が寄せられました。根も葉もないデマを流し外国人を攻撃するやり方に、記者会見で各知事からの批判や懸念の表明が相次ぎました。7月に開催された全国知事会議の成果をまとめた「青森宣言」には「排他主義、排外主義を否定し多文化共生社会をめざす」と明記されました。
本市としても、川崎市人権尊重のまちづくり条例の立場に立ち、排外主義を否定し、デマや差別を許さないとの毅然とした対処が求められます。市長に伺います。また、選挙期間中に見られたような、条例の罰則規定に抵触しないヘイトスピーチであっても、外国人に対する憎悪を煽る言動や不当な差別的言動は許されないという姿勢を改めて示すべきではないでしょうか。市長に伺います。
川崎市内の朝鮮学校への運営費補助金の復活についてです。
川崎市は、2012年度まで、朝鮮学校に対し、運営費の補助を行っていました。しかし、神奈川県が補助金を打ち切ったことに伴い、就任直後の市長は2013年度に計上されていた運営費補助金を凍結、翌年度、運営費補助を廃止しました。その代わりに、健康診断に要する費用や地域交流のための補助金になり、当初、840万円あった補助金は236万円と、4分の1近くになってしまいました。
その結果、学校の運営はひっ迫し、校舎の修繕や教員の給料の支払いにも困難をきたし、保護者負担は授業料等を含め月額3万円を超え、経済的理由で朝鮮学校に通うことのできない子どもも生じています。
川崎市の朝鮮学校に対する補助金は、すべての者の教育を受ける権利をうたった国際人権条約を日本が批准した翌年1980年から交付されています。まさに、人権の問題として始まりました。「川崎市子どもの権利に関する条例」では、「子ども又はその家族は、国籍、民族…などを理由とした差別及び不利益を受けないこと」が明記されています。こども未来局長は、昨年6月議会において、「条例の対象とする子ども」に「外国人市民の子どもも含まれる」と明言しています。神奈川県が補助をやめたからと運営費補助を打ち切ることは、本市の子どもの権利条例はもとより、外国人教育基本方針などに反しているのではないですか、市長に伺います。「こどもの権利」という立場から、運営経費への補助を復活すべきと思いますが、市長に伺います。
市内2つの朝鮮学校は、来年80周年を迎えます。地域住民とともに、多文化共生、交流事業を担う、長く歴史のある朝鮮学校は他になく、川崎市の誇るべきことです。多文化共生の拠点としての役割を発揮し地域教育資源を活かした取り組みを行っています。教職員や保護者は、「市長に、ぜひ一度学校を訪れて頂き子どもたちの学びや活動をご覧いただきたい」と願っています。市長の対応を伺います。
障がい者施策についてです。
障がい者福祉サービスにおける、介護ヘルパーの不足は深刻です。重度訪問介護、同行援護、行動援護など、重度障がい者にとって生活するだけでなく生きていくうえでもどうしても必要な介護が、人手不足でできない事態は、なんとしても解消しなければなりません。重度訪問介護を24時間受けて一人暮らしをしている方は、ヘルパーの絶対数が足りないために、ヘルパーが病気になるなどシフトに入れなくなると代わりの人がいないので、ご本人はトイレにも行けず食事もとれなくなるということです。この間、介護人材確保や定着に関する取り組みをしていると言われますが、当事者からは「その実感はない」と言われています。抜本的な処遇改善を行い、他の産業と肩を並べるような給与を保障するよう市として補助すること、専門職としてスキルを身に着けた人材を育成するよう、研修の機会を増やすべきですが、伺います。
高齢者施策についてです。
特別養護老人ホームについてです。
8月1日現在の待機者は要介護4が675名、要介護5が461名を含む2187名です。依然2000名前後の方が待っています。一方、全市59の特養ホームの入居稼働率は95.9%でほぼ満床です。今年度まで296床増やす整備計画をしているとの答弁がありました。待機者の人数と稼働率から見て、この計画整備数は特養ホーム自体が足りているという認識なのか伺います。
政府の統計によると推計する介護職員の必要数に対し2026年度には約25万人が不足するとしています。本市ではどれくらいの人数が不足すると推計しているのかうかがいます。介護職員の確保は待ったなしです。市民から「介護職を目指している娘が「居住支援特別手当」など、処遇の良い東京都で仕事を決めた」と聞きました。介護職の処遇面でも多摩川格差が起こっています。流出を防ぐためにも東京都のような独自支援策の検討が必要ではないでしょうか。伺います。
高齢者世帯及び障がい者世帯へのエアコン設置助成についてです。
本市の今年6月~8月の熱中症で救急搬送された人数は速報値で584人。この内、室内で発症された65才以上の方は137人に上ります。137人の中で、エアコン設置なしが25世帯、1名の方がお亡くなりになっています。9月以降も高温が続くとされています。こうした高温化の中で他の自治体では、高齢者や障がい者世帯の熱中症対策としてエアコン設置補助が進んでいます。東京都は熱中症対策として、この8月30日から、エアコンのない65歳以上を対象に、エアコンの購入費用をそれまでの1万円から8万円に引上げ補助します。前議会の質問に「国や他都市の動向を注視しでまいりたい」との答弁でした。本市も、市民の命に関わる問題として捉え、高齢者や障がい者世帯へのエアコンの購入費用補助を今からでも、実施することを求めます、伺います。
議案第144号 令和7年度一般会計補正予算(9月補正)についてです。
医療機関物価高騰対策支援事業費が組まれました。医療機関の光熱費の負担軽減を図るものとして実施されます。しかし、対象は有床の病院、診療所とし、ベッドの無い無床診療所には適用されません。病院だけでなく診療所も非常に厳しい経営状況です。無床診療所からは、医薬品、医療材料費の値段が1.2~1.7倍と高騰している。今年はもっと経費が増えると予想される、いつまで続けられるか閉院を検討中など地域医療の崩壊に繋がりかねない実態があります。今回の補正予算を増額し、無床診療所も対象にすべきです、伺います。
中小企業支援についてです。
物価高騰による材料費や人件費の増加は、中小、とりわけ小規模事業者の事業継続を脅かしています。この「物価高騰」や「賃上げ」に対する自治体の支援が拡がっています。6月議会でも紹介した岩手県の「賃上げ支援金」のほかにも、武蔵村山市では、物価高騰の影響を受けた市内事業者に、法人で一律5万円、個人事業者に一律3万円を給付します。調布市でも、事業所の“ある月”の経費を6倍にした金額の20%を、法人で30万円、個人事業主で10万円を限度に支給。そのほかにも、政策金融公庫から借りた融資の利子分を20万から50万円を限度に支給する仙台市など、様々な取り組みが自治体で行われています。市長は「経営基盤の強化が必要」と繰り返し答弁されてきましたが、苦境に立たされている市内中小・小規模事業者が今を乗り切る「給付事業」に踏み出すべきです。市長に伺います。
公契約制度の運用改善についてです。
公契約制度は本市において「労働者の賃金を担保することで公共事業の品質の確保、地域経済の発展を図り、市民の福祉の増進に寄与するために」必要な制度であることをこの間の議論で繰り返し確認をしてきました。
市内建設組合が行った大手企業交渉の中で、条例の対象となる企業では、本人申告の職種で解体工の日給が21,992円のところ12,500円、内装工27,784円のところ14,000円しか払っていないことが明らかになりました。その企業からも作業報酬下限額が支払われていない実態を認めた発言があったとのことです。
制度の趣旨からしても大問題であり、この事態を重く受け止め早急な改善が求められます。作業報酬下限額が担保されない理由として、一つ目には元請け以外の最終下請けまでに公契約条例遵守の周知がされていないとの指摘があります。千代田区では元請けが下請け対し条例遵守の依頼文を発出し周知しています。本市でも元請けだけではなく、最終下請けまで周知すべきです、伺います。また、2次3次などの下請けからはこの発注額では、決められた作業報酬下限額を支払うことができないとの声も届いています。本市の責任で、最終下請けまで聞き取りをおこない実態を把握して検証をおこなうべきです。伺います。
2つ目の理由として、条例を十分に理解していない現場従事者が見受けられていることが指摘されています。周知については配布するチラシの改善などを行っているとのことですが、それではまったく不十分です。厚木市や相模原市では市の職員と公契約条例審議委員が合同で現場訪問を行い周知を進める取り組みを行っています。以前より提案を行ってきましたが、本市も現場訪問をおこない、実態を把握し改善策につなげるべきです。伺います。また、2018年に制度理解や実効性を確認するために本市がおこなったアンケートを再度実施することも有効です。この間「適切な時期に実施する」との答弁が繰り返されています。7年も経ちこれ以上の曖昧な対応は許されません。適切な時期とはいつなのか具体的に伺います。
防災対策についてです。
線状降水帯が発生し、1か月間の降水量がわずか半日で降るような豪雨がこの夏、各地で起きました。地球温暖化による気候変動により考えられないような降雨がどこでも起こりえます。これまで以上の水害対策が喫緊の課題です。
水害時の住民の避難は、台風なら何日も前に予想できるので、事前に食料なども用意して3階や4階のある避難所へいくということになっています。しかし今回の経験は、あっという間に川が増水してくるというものであり、万一多摩川や市内の河川が増水してきた場合、遠くの避難所まで行くことができるのか、しかもその避難所に入り切れるのかということが問題になります。そこで、公的施設は開放し、津波避難ビルのように近所のマンションや民間のビルと協定を結んで、高いフロアを開放してもらう提携を行うべきと考えますが、伺います。
災害時のトイレ対策についてです。8月28日の総務委員会で本市の災害時のトイレ対策方針案が示されました。2031年をめどに全ての避難所を含めた155カ所にマンホールトイレを設置していくとのことですが、担当する危機管理本部の人員は課長含め5名とのことです。設置を担当する上下水道局も含め、遅れることなく確実な整備を行っていく人員体制等は確立されているのか伺います。
トイレ対策方針にはスフィア基準に沿った取組が盛り込まれましたが、スフィア基準はトイレ対策だけではありません。今後も居住スペースや飲料水の確保等、スフィア基準に沿った避難所整備を進めていくのか伺います。
議案第128号 災害用携帯トイレの取得についてです。
携帯トイレを各避難所に2日分の備蓄をすることになっていますが、上下水道が2日で復旧するかどうかは本当にわかりません。また、在宅避難している人たちもトイレが使えなければ避難所のトイレを利用すると思われます。携帯トイレの備蓄は抜本的に増やすべきですが伺います。
議案題120号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
この議案は、地区計画を定める都市計画決定に伴い、等々力緑地公園地区整備計画区域を新たに条例の適用区域として追加し、建築物の用途の制限の緩和等を可能とするものです。
前提となっている都市計画決定では、地域地区の変更が行われていますが、これにより、建設できる店舗等の合計床面積が500㎡から10000㎡以下に緩和されることになります。この変更によって、例えば飲食店等の店舗が伴う大型公衆浴場、いわゆるスーパー銭湯の建設が可能になるという解釈でよいのか伺います。
地球温暖化対策としての街路樹の整備についてです。
前の議会で、樹冠被覆率という考え方を提案しました。樹冠被覆率とは一定面積の地面に対して高木の枝や葉が茂っている部分が占める割合を指し、ニューヨーク市は2030年までに30%、メルボルン市は2040年までに40%と目標を持って取り組んでいます。樹冠によって生まれる木陰が地上への日射を抑制し、気温の上昇を抑える効果は顕著で、研究者の調査では直射日光の当たる路面温度は50℃を越えているところで、樹冠の被覆によって路面温度が20℃下がります。また別の研究者は「樹冠被覆率を30%まで増やせば暑さに起因して亡くなる人を約40%減らせる」と言っています。本市のような都市部では街路樹が肝要です。そのためには、植える道路の環境、せん定の強度、落ち葉の処理など、樹木の種類や成長の度合いによってさまざまな対応が必要とのことです。東京都は「街路樹等維持標準仕様書」などで樹冠被覆率をあげるような街路樹のせん定基準などを明らかにしています。建設緑政局長は「研究する」との答弁でしたが、東京都などを参考にして、温暖化対策に資する街路樹管理へ転換すべきですが伺います。
羽田新飛行ルートについてです。
2020年3月に運航が開始され5年半が過ぎようとしています。南風時の15時から19時まで、1日あたりの便数は60便を上限としています。国土交通省からの直近までのデータによれば、2024年7月には29日間で1日あたり約53便、8月には25日間で約46便が運航されており、ほぼ毎日85㏈前後の騒音を発生させながら、住宅街上空をパチンコ店の中にいるかのような音を立て3分間隔で運航が行われています。
離陸直後は石油コンビナート上空を通過します。世界の航空事故の大半が離陸後3分間、着陸前8分間に集中しています。けが人や事故はなかったものの、今月2日に離陸直後のボーイングがエンジントラブルを起こし緊急事態を宣言し羽田に引き返しました。また、わが党の国会議員からの国交省の調査によると、2024年度の羽田空港で発見された部品欠落は580件にも上がっています。墜落事故や落下物などで万が一の事故が起こった場合、石油コンビナート地帯で働く労働者や住民の命の危険とともに、約27万人が避難を必要とする可能性があります。「すごい低空すぎて今にも落ちてきそうだ」「ここは安心して住める場所ではない」と不安の声が相次いでいます。
住民や労働者が命の危険と隣り合わせで生活せざるを得ない状況をつくったのは市長です。1960年代に航空事故が相次ぐ中、市民の運動と市議会が全会一致で意見書を上げ、当時の市長も一体となり運動をおこし、1970年代に東京航空局長から「原則として石油コンビナート上空は飛行しない」旨の通知が発出されました。この通知によって川崎区は50年間安全な空が守られてきました。しかし、市民や議会に諮らずにこの通知を勝手に反故にしたのが市長です。市長はこれまで「羽田空港の機能強化の必要性を認識している、安全対策等を国に求めている」など、新飛行ルートを認める答弁を繰り返してきました。このまま、住民や労働者への負担押し付けを続けるつもりですか、市長に伺います。自治体の長として、国の言いなり、市民の命や安全を国へ責任転嫁する姿勢はこれ以上許されません。海上ルートに戻すように国に要望すべきです、市長に伺います。
以上で質問を終わります。